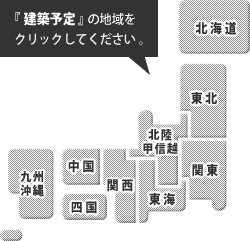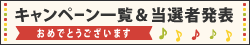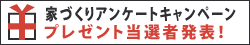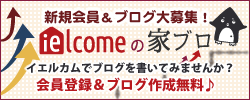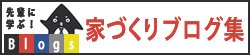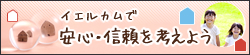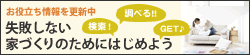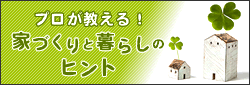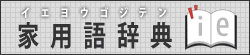イエルカムで安心・信頼を考えようRelieve&Trust

リフォーム・リノベーションを行うと、所得税の控除を受けられる場合があります。リフォーム・リノベーションの所得税減税には、『投資型減税』『ローン型減税』『住宅ローン減税』の3つの種類があります。住宅ローンの償還期間(しょうかんきかん:返済期間)が10年以上あると利用できるのが、住宅ローン減税です。住宅ローン減税は、2014年4月からの消費税増税にあたり大幅に控除額が引き上げられました。リフォーム・リノベーションの所得税控除を受ける場合は、入居した年の収入についての申告を行う翌年の確定申告時に、税務署への確定申告で手続きをします。利用するポイントを確認しましょう。
※2014年4月時点の情報です。
- 所得税とは?
- その年の1/1~12/31の一年間に得た個人の所得(収入から必要経費を差し引いた額)に対して課税される税金(国税)です。会社員の場合、二年目からは会社にローンの残高証明を提出すると年末調整で控除を受けられます。
まずは住宅リフォーム・リノベーションの所得税控除を利用できるかチェック!

利用できるリフォーム・リノベーションの所得税減税は、住宅ローンを利用するか否か、住宅ローンの返済期間、またそのリフォーム・リノベーションの種類によって決まります。まずは、減税制度のタイプを確認しましょう。
※投資型減税・ローン型減税についてはこちらをご覧ください。
リフォーム・リノベーションの種類に関係なく、要件を満たすと利用できるタイプ
 住宅ローン減税
住宅ローン減税
10年間、控除が受けられる! 控除額が大幅にUP!
10年以上の償還期間のある住宅ローンを借り入れたときに、所得税の控除を10年間受けられる減税制度です。
主な利用条件
居住開始期間
2013/1/1~2017/12/31
2009/1/1~2012/12/31居住開始分も、控除対象額限度額は異なり
ますが、適用期間です。
控除期間
改修後、居住を開始した年から10年
控除対象限度額
2014/3/31まで2,000万円
2014/4/1~2017/12/31 4,000万円
※ただし、消費税率5%が適用される場合は2,000万円
控除率
年末ローン残高の1%
実際の控除額
上限額 13.65万円 / 1年 (前年課税所得×7%)
※2014/3/31まで、または消費税率5%適用の場合は
9.75万円 / 1年 (前年課税所得×5%)
(年末ローン残高‐補助金等)×1%
- ※ ここでの補助金とは、国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるものをいいます。
- ※ 住宅ローン控除額まで所得税から控除できない場合は、翌年の住民税からも控除できます。
 利用できるリフォーム・リノベーションの各要件をチェック!
利用できるリフォーム・リノベーションの各要件をチェック!
耐震リフォーム、省エネリフォーム、バリアフリーリフォームはもちろん、要件を満たせばリフォーム・リノベーションの種類に関係なく、また新築や中古住宅を購入時にも利用できます。

- 対象となる改修工事
-
- ・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
- ・マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- ・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- ・耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
- ・ローン型減税対象のバリアフリー改修工事
- ・ローン型減税対象の省エネ改修工事
- 工事費について
-
- ・居住用の工事費が改修工事総額の1/2以上であること。
- ・対象となる改修工事費用が100万円を超えること。
※2011/6/30以後に契約した工事の場合は補助金等を控除した額。
- その他
-
- ・自らが所有し、居住する住宅であること。
- ・改修工事後の床面積が50㎡以上あり、その1/2以上が居住用であること。
- ・改修工事完了した日から6か月以内に入居すること。
- ※適用後、転勤等やむを得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合についても再適用が可能。また住宅の居住の用に供した年の12/31までの間に、転勤命令等のやむを得ない事由により転居し、その後再び当該住宅に入居した場合にも適用可能。
- ※住宅を居住の用に供する前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供した場合にも、住宅ローン減税制度の適用可能。
- ・合計所得が3,000万円以下であること。
リフォーム・リノベーションの所得税減税の利用要件は、改修工事の種類や工事費、住宅ローンの利用の有無などによって細かく定められています。タイミングや工事の効率を考え、耐震リフォームと省エネリフォームを一緒にするケースもあるでしょう。同時に種類の異なるリフォームを行うと控除される金額が変わったり、併用して利用できない支援制度もあります。どの組み合わせが自分たちに合っているのかを含め、依頼する住宅パートナーさんやお金に専門家であるファイナンシャルプランナーさんに相談してみると良いでしょう。